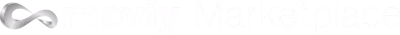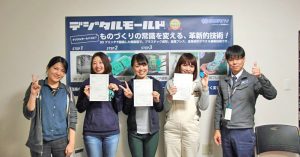デジタルモールド®は、長野県の有限会社スワニーの特許技術で、3Dプリンターで造形した樹脂型で射出成形を行う工法です。試作品を量産品と同じ材料で早く安く作りたい、あるいは小ロット生産を低コストで行いたいという現場のニーズに応えるソリューションで、製造業の製品開発において注目を集めています。
本記事では、デジタルモールド®の仕組みや特徴、メリット・デメリットについて解説します。また、具体的な活用事例や他の加工法との比較、導入時のポイントにも触れるので、部品設計を担当している方はぜひ最後までご覧ください。
目次
デジタルモールド®とは何か
デジタルモールド®の定義と仕組み
デジタルモールド®とは、3Dプリンターで造形した樹脂製の型を用いて、ABSやPP(ポリプロピレン)といった熱可塑性樹脂を射出成形する技術です。有限会社スワニーが特許取得し、商標登録もしています。
仕組みは、金属の代わりに光硬化樹脂などで作られた樹脂の型を射出成形機にセットし、量産品と同じプラスチック材料を射出して部品を成形するというものです。従来、プラスチックの量産には高耐久な金属金型が用いられていたものの、製作には莫大な時間とコストがかかりました。デジタルモールド®は、金型製作のプロセスを3Dプリンターによるデジタル造形に置き換え、圧倒的なスピードと低コストを実現しています。
デジタルモールド®と従来の射出成形との違い
デジタルモールド®と従来の射出成形との大きな違いは以下のとおりです。
|
項目 |
デジタルモールド® |
従来の射出成形(金属金型) |
|
金型の材質 |
3Dプリンターで造形した樹脂 |
鋼鉄などの金属 |
|
頭出し(T0)品までの製作期間 |
非常に短い(最短3日) |
長い(数週間〜数ヶ月) |
|
初期コスト |
低い |
非常に高い |
|
耐久性(ショット数) |
少ない(数十〜数百程度) |
非常に高い(数万〜数十万ショット) |
|
得意な用途 |
試作、小ロット生産 |
大量生産 |
上記のように、両者は金型の材質や製作プロセス、得意とする生産領域が異なります。デジタルモールド®は、金型製作のデジタル化により、従来工法では対応が難しかった「試作・小ロット生産」の領域に特化した新しい選択肢といえます。
なぜ今デジタルモールド®が注目されているのか
デジタルモールド®が注目を集めている背景には、以下の点が考えられます。
- 技術の成熟
高精度・高耐熱な材料が開発され、3Dプリンターの性能が向上したため、射出成形の圧力や熱に耐えうる実用的な樹脂型の造形が可能になりました。 - 市場ニーズの変化
消費者ニーズの多様化に伴い、製造業は「大量生産」から「多品種少量生産」へのシフトを迫られています。製品ライフサイクルが短くなる中、小ロットでも迅速に市場投入できるデジタルモールド®は、時代の要請にマッチした技術といえます。
- 実績と信頼性の向上
大手企業での採用事例が増え、有効性が広く認知されるようになりました。たとえば、ある大手メーカーでの試作では開発期間を4〜6ヶ月から約3週間に短縮した実績があります。
- サービス提供体制の整備
ミスミの「meviy(メビー)」をはじめとするオンラインの加工プラットフォームが、デジタルモールド®に対応し始めたため、設計者がより手軽に利用できる環境が整いました。
デジタルモールド®の加工フローと特徴
加工の流れ(CAD設計〜成形〜仕上げ)
デジタルモールド®による加工は、主に以下の流れで実施されます。
- 製品3Dデータの準備と型設計
まずは、成形したい製品の3D CADデータから、樹脂型用の3Dデータを設計しましょう。 - 樹脂型の3Dプリント造形
設計データを3Dプリンターに送り、光硬化樹脂などで型を造形します。 - 樹脂型の仕上げ・組み立て
必要に応じて型の表面を切削加工で仕上げ、精度を高め、金属製のモールドベースに組み込みます。 - 射出成形
組み立てた型を小型の射出成形機にセットし、材料や成形条件を調整しながら試し打ちを行ってください。 - 本成形と仕上げ
最適な条件で必要数を成形し、ゲートカットなどの仕上げを施して完成です。
使用される樹脂型(シリコン型・簡易金型など)
デジタルモールド®で用いられる樹脂製の型は、3Dプリンターによって造形される特殊な型です。樹脂型と対比される存在に、シリコン型やアルミ簡易金型など他の型もあります。それぞれの違いについて整理します。
- 3Dプリント樹脂型(デジタルモールド®)
射出成形に使える点が最大の特徴です。量産材料で、ある程度の数を迅速に成形したい場合に適しています。
- シリコン型(真空注型)
マスターモデルから型を作るため初期費用は安いものの、ウレタン樹脂など特殊な材料に限られ、生産性は低い傾向にあります。
- アルミ簡易金型
数百〜数千ショットの中ロット生産に対応可能です。ただし、製作に1〜2週間を要し、コストも樹脂型より高くなります。
- 鋼製簡易金型
構造を簡略化した鉄製の金型で、1万ショット以上に対応可能です。品質は高い一方で、コストと納期はアルミ型よりかかります。
デジタルモールド®の短納期・低コストを実現できる理由
デジタルモールド®が短納期・低コストを両立できる理由は、主に以下の3点です。
- 金型製作プロセスの簡略化
NC加工機による切削や職人の手仕上げといった、時間と人手を要する工程が不要です。3Dプリンターが自動で型を造形するため、プロセスが大幅に簡略化・短縮されます。
- 初期投資の低減
高価な金属材料や精密加工が不要となり、型の製作費用を圧縮できます。これまでコスト面で断念していたような試作にも着手可能です。
- 設計変更への柔軟性
試作品の評価後に設計変更が必要になっても、CADデータを修正して再度3Dプリントするだけで、迅速かつ安価に新しい型を製作可能です。開発段階でのトライ&エラーが容易になるため、開発スピードの向上をもたらします。
対応可能な材質と形状
ここからは、デジタルモールド®で対応可能な材質と形状について見ていきましょう。
使用できる材料の種類(PP、ABS、エンプラなど)
デジタルモールド®は、PP、ABS、PS(ポリスチレン)、POM(ポリアセタール)といった汎用樹脂から、PC(ポリカーボネート)やPA(ナイロン)などのエンジニアリングプラスチックまで、幅広い熱可塑性樹脂に対応可能です。ただし、ガラス繊維強化材や超高融点のスーパーエンプラは、樹脂型を著しく摩耗・劣化させるため、使用には注意が必要です。
形状自由度や寸法精度の特徴
形状の自由度は、基本的には従来の射出成形に準じます。抜き勾配を設けたり、アンダーカット形状を避けたりといった射出成形特有の設計ルールを守らなければなりません。寸法精度は±0.1〜0.2mm程度が一般的で、機能検証には十分なレベルであるものの、金属金型ほどの高精度は期待できません。
量産前提の試作か、最終製品かによる使い分け
量産を前提にした試作か、最終製品の生産かによって、デジタルモールド®の使い分けが必要です。
量産前提の試作で用いる場合には、将来的に金属金型へ移行することを見据え、設計の妥当性検証や問題点の洗い出しを目的とします。多少の品質の甘さは許容しつつ、量産時のリスク低減につなげます。
一方、最終製品としての生産では、小ロット製品や限定品として市場に供給するため、製品としての品質を追求します。型の仕上げや成形条件の最適化を丁寧に行い、品質保証体制も整えなければなりません。
他の加工法との比較
デジタルモールド®と従来の射出成形との比較
デジタルモールド®は「少量・短期・低コスト」の領域で強みを発揮し、従来の金属金型による射出成形は「大量・長期・高品質」の領域を担います。開発初期段階でデジタルモールド®を活用し、量産移行時に金属金型へ切り替えるといったハイブリッドな使い方が有効です。
デジタルモールド®と切削加工との比較
1〜数個の試作であれば、切削加工の方が速くて安い場合があります。ただし、10個以上の同じ部品を作る場合は、ひとつずつ削る切削加工に対し、型を作れば繰り返し成形できるデジタルモールド®の方が効率的です。また、切削では加工不可能な複雑な形状でも、射出成形なら一体で製造できる場合があります。
デジタルモールド®と3Dプリントとの比較
3Dプリントは手軽で迅速に形状を確認できる手法である一方、材料の物性が量産品と異なる点が課題です。デジタルモールド®は量産と同じ材料で成形できるため、強度や耐久性といった機能評価の信頼性が高まります。デザイン検討の初期段階では3Dプリント、機能検証の段階ではデジタルモールド®という使い分けが理想的です。
デジタルモールド®と注型との比較
真空注型は、金属金型を使わずに小ロット(約10~100個)の部品を作る工法です。初期費用が低く、微細形状の再現性に優れます。一方、材料は熱硬化性ウレタンのため、ABSやPPなど量産材と物性が一致せず、強度・耐熱の評価互換性が低くなります。デジタルモールド®は量産と同じ熱可塑性樹脂で射出できるため、量産品同等の物性で機能評価が可能であり、小ロットの製品供給にも対応できます。
デジタルモールド®のメリット・デメリット
メリット(コスト削減・短納期・柔軟性ほか)
デジタルモールド®の主なメリットは以下のとおりです。
- 初期コストの大幅削減
数十万〜数百万円の金属金型費用を数万〜数十万円程度に抑えられ、開発の初期投資リスクを低減できます。
- 圧倒的な短納期
設計データがあれば最短数日で成形品を入手可能です。開発リードタイムを短縮し、市場投入までのスピードを加速させます。
- 量産品と同じ材料・製法で試作可能
ABS、PP、PCなど量産品と同じ樹脂材料で成形するため、3Dプリント品では難しかった強度や耐久性の評価を、試作段階で正確に実施可能です。
- 小ロット生産の実現
数十〜百個単位の生産を低コストで行えるため、市場テストや限定品、補修部品の製造といった用途に最適です。
- 設計変更・バリエーション展開への柔軟性
型の作り直しが容易なため、設計変更に柔軟に対応できます。また、ロゴや仕様が異なる複数パターンの製品を低コストで同時に試作可能です。
デメリット(耐久性・量産非対応など)
一方で、デジタルモールド®には以下のようなデメリットがあります。
- 樹脂型の耐久性限界
デジタルモールド®の弱点は、型の寿命の短さです。成形材料や部品形状により異なるものの、型の摩耗・劣化により、数千個以上の量産には向きません。
- 成形品精度・仕上がりの制約
樹脂型は剛性や熱伝導率が金属に劣るため、寸法精度や表面品質は金属金型に一歩譲ります。特に高い外観品質が求められる部品には注意が必要です。
- 対応サイズの制限
3Dプリンターの造形エリアや小型成形機の仕様から、成形できる部品サイズは10cm角程度に限定され、大型部品には対応できません。
- 材料・成形条件への注意
ガラス繊維を多く含む樹脂や、PEEKなどの超高耐熱スーパーエンプラは、型への負荷が大きく、使用が難しい場合があります。
活用に向いているケース/向いていないケース
ここでは、デジタルモールド®が向いているケースと、向いていないケースについて解説します。活用に向いているケースは以下のとおりです。
- 機能・強度検証を目的とした試作
量産材で成形するため、ヒンジの耐久性や嵌合(かんごう)の感触など、実製品に近い条件で評価したい場合に最適です。
- 100個程度の小ロット生産・市場テスト
金型投資が抑えられるため、テスト販売やニッチな需要に応える限定品の生産に向いています。
- カスタム品・補修部品
ロゴ入れなどのカスタマイズや、生産終了品の保守用パーツなど、必要な数だけをオンデマンドで供給したい場合に有効です。
一方で、以下のようなケースには向いていません。
- 数千個以上の大量生産
ショット数の限界から、初めから金属金型を製作する方がトータルコストで有利です。
- 高精度・高外観が求められる製品
光学部品や高級家電の外装など、ミクロン単位の精度や鏡面仕上げが必要な場合には向いていません。
- 大型部品
自動車のバンパーや家電の筐体など、手のひらサイズを超える大きな部品の成形は困難です。
向き不向きを理解して、適切な場面でデジタルモールド®を活用しましょう。
活用事例と用途別の選定ポイント
自動車部品、家電、医療機器などの試作事例
デジタルモールド®は、「短納期」と「量産材料での試作」という強みを活かし、さまざまな業界で活用が進んでいます。代表的な分野における活用事例は以下のとおりです。
|
分野 |
主な用途 |
活用のメリット |
|
自動車 |
機能部品(クリップ等)の耐熱・耐振動試験用試作 |
量産材による高精度な機能評価で、開発の信頼性を向上 |
|
家電・電子機器 |
新製品の筐体や機構部品の試作 |
開発サイクルを高速化し、製品化のスピードを向上 |
|
医療機器 |
少量多品種・カスタム品の製作 |
低コストで少量・カスタム品の開発が可能に 滅菌等の実用に近い検証も実現 |
|
玩具 |
精密なデザイン試作 |
開発期間を短縮し、市場投入のスピードを加速 |
少量生産・市場テスト製品への活用
デジタルモールド®は、本格量産前の市場調査や、ニッチな需要に応えるための製品供給にも有効です。従来は金型コストが障壁となり実現困難だった「100個だけ作ってテスト販売する」といった戦略が、デジタルモールド®によって現実化されます。
また、生産終了した製品の保守部品を、金型がなくても3Dデータから必要な数だけ生産するといった活用法も可能です。
用途別判断マトリクス(コスト・納期・目的別)
試作や少量生産には複数の手法があります。主な手法の違いについて、以下の表にまとめました。
|
項目 |
デジタルモールド® |
射出成形(金属金型) |
切削加工 |
3Dプリント |
|
初期コスト |
低い |
非常に高い |
ほぼゼロ |
極めて低い |
|
1個あたりコスト |
中程度 |
極めて低い(量産時) |
高い |
やや高い |
|
リードタイム (製作期間) |
非常に短い(最短3日) |
長い(数週間〜数ヶ月) |
短い |
非常に短い(数時間〜) |
|
対応数量 |
〜100個程度 |
大量生産向き |
1〜10個程度 |
1〜50個程度 |
|
使用材料 |
量産と同じ樹脂 |
ほぼ全ての樹脂 |
樹脂、金属など |
造形材料に限定 |
|
寸法精度・仕上がり |
良好 |
非常に高精度 |
高精度 |
中程度(積層痕あり) |
|
主な用途 |
機能試作、小ロット生産 |
大量生産 |
デザイン・高精度試作 |
形状確認、デザイン検討 |
※上記は一般的な目安です。
導入時の注意点と選定ガイド
品質トラブルを防ぐための設計上の注意点
デジタルモールド®を成功させるには、樹脂型の特性を理解した設計が不可欠です。金属型より離型抵抗が大きいため、十分な抜き勾配を設けましょう。また、型の破損を防ぐため、シャープなエッジや極端な薄肉形状は避けるべきです。充填不良やヒケといった品質トラブルを防ぐには、肉厚を均一にし、樹脂が流れやすいゲート位置の検討が重要です。射出成形の基本ルールを守りつつ、樹脂型への負荷を減らす配慮が品質を左右します。
金型不要=ノーリスクではない点に注意
デジタルモールド®は金属金型製作を回避できるものの、ノーリスクではありません。射出成形である以上、製品設計に起因する充填不良やソリといった品質問題は起こり得ます。また、樹脂型は消耗品であり、成形中に破損する可能性も考慮すべきです。安易な手戻りは、コストや時間の浪費につながりかねません。デジタルモールド®を万能な解決策と過信せず、従来のものづくり同様に、リスクを管理しながら計画的に活用してください。
デジタルモールド®の見積もり依頼は「meviyマーケットプレイス」へ
メビーマーケットプレイスはデジタルモールド®に対応
ミスミの「meviy Marketplace(メビーマーケットプレイス)」の射出成形サービスでは、デジタルモールド®を選択できます。最短3日目出荷を実現する最速工法で、小ロット(〜100個)の製造が可能です。メビーマーケットプレイスは、製造パートナーから“あらゆる機械加工部品をワンストップで手間なく”手配できる、日本最大級の製造業マーケットプレイスです。
新規の口座開設なしで、条件にマッチしたパートナーと直接やり取りして手配できるため、機械加工部品調達の手間を大幅に削減することができます。ぜひお試しください。
製作事例
デジタルモールド®を採用した製作事例は以下のとおりです。
|
|
|
|
部品名 |
ラジコンカーホイール |
|
材質 |
ABS |
|
数量 |
100個 |
|
サイズ |
X45×Y45×Z10mm |
|
工程 |
型費:300,000円、成形:500円/個 |
|
出荷日 |
3日目 |
まとめ
デジタルモールド®は、3Dプリンターで樹脂製の型を造形し、射出成形を行う工法です。最大の特徴は、従来数週間以上かかっていた型製作を最短1日に短縮し、量産品と同じ材料を用いた試作品を低コストで製作できる点にあります。
主なメリットは、開発初期のコスト低減や、設計変更への柔軟な対応力です。一方で、樹脂型の寿命は数百〜数千程度と短いため、大量生産には向きません。寸法精度や外観品質は金属金型に及ばない点にも注意が必要です。
そのため、3Dプリントによる形状確認、デジタルモールド®による機能試作、そして金属金型による大量生産といった、開発フェーズに応じた「適材適所」の使い分けが成功の鍵となります。
本記事の内容を参考にして、多品種少量生産が求められる現代のものづくりにおいて、開発プロセスを変革する強力な選択肢であるデジタルモールド®を使いこなしてください。