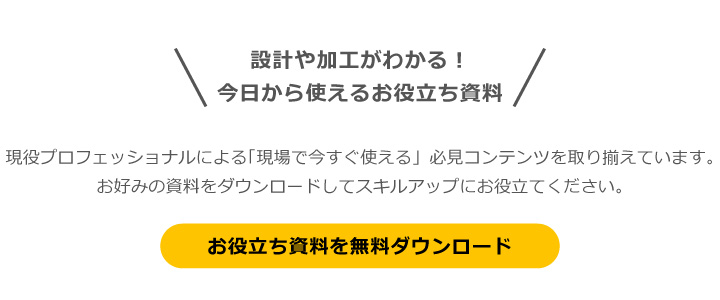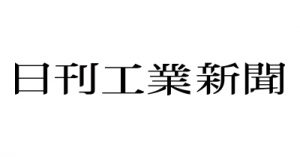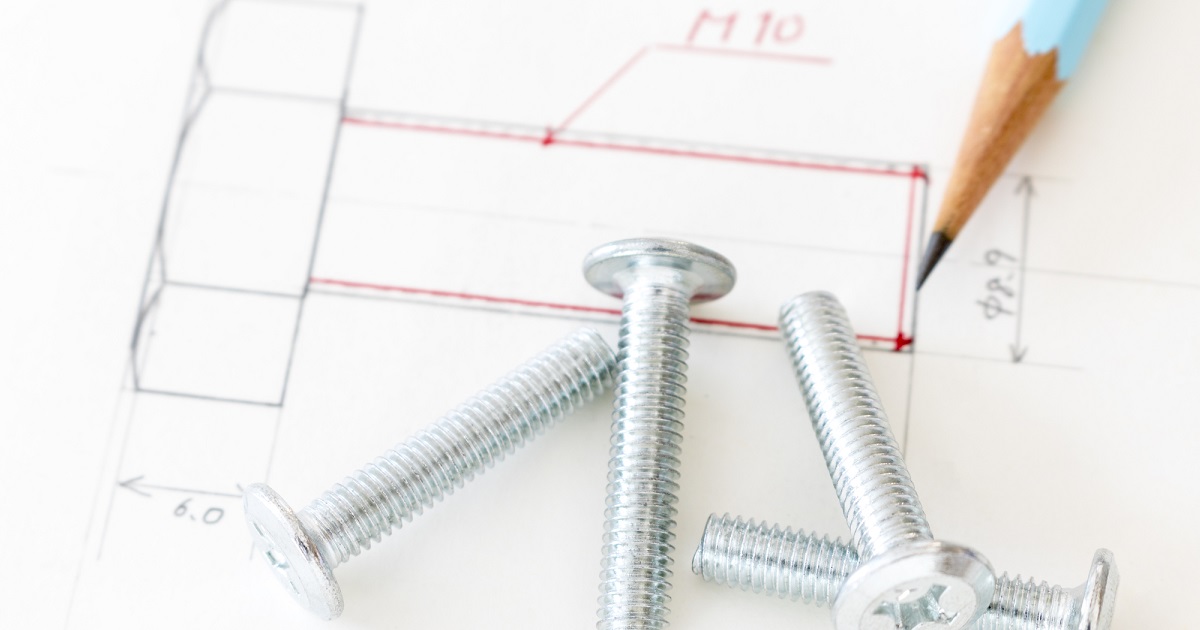「部品表の管理がExcelでは限界」「部門ごとに形式がバラバラ」などの悩みを抱えている方もいるでしょう。この記事では、部品表の基本的な概要から、設計・購買・製造といった各部門での役割、部品表システムを導入するメリットまでを解説します。
この記事を読めば、部品表を一元管理し、業務効率を飛躍的に向上させるためのヒントが得られるはずです。設計・開発担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
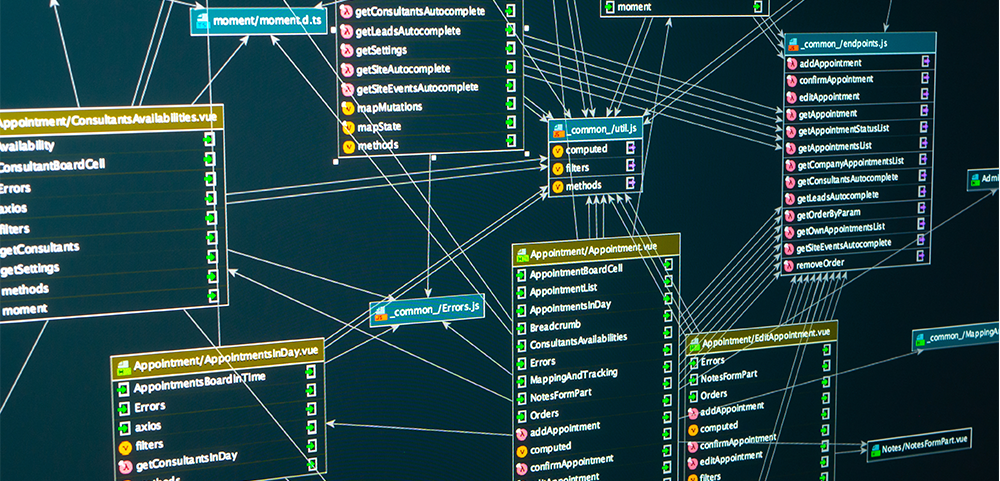
目次
部品表(BOM)とは

部品表(BOM: Bill Of Material)とは、製品に使われる部品の全ての記録を集約したデータベースを意味します。部品表は単に構成部品の情報だけでなく、部門間の情報共有に役立っています。
まだ 紙図面が使われていた時代には、部品表とは文字通り部品の全てを記した表を意味していました。図面の隅に記載されていた一覧表です。部品の材質や詳細を記した単品図面の図面番号など、必要な情報が記載されていました。
そこから転じて、近年では部品表とは、製品に使われる全ての部品に関して、図面データや、その部品が使用される製品の一覧、購買先情報や工程情報など、あらゆるデータを集約したデータベースを意味するようになりました。
さらに設計で使うCADや図面閲覧システム、生産技術や購買部門が使う販売システムや購買システムとも連携し、現在は効率的なものづくりに欠かせないシステムになっています。
部品表の役割と用途

部品表は複数の部門で活用され、重要な役割を果たします。ここでは、部品表の基本的な運用と、各部門における具体的な活用方法を見ていきましょう。
部品表運用の基本
部品表運用の基本は、固有の「部品番号」で全部品を一元管理する点にあります。部品番号を検索キーとして、関連する図面データや材質仕様、仕入先、使用先といったあらゆる情報を紐づけます。
一元化により、部門ごとに散在しがちな情報が集約されるため、認識のズレがなくなります。例えば、ある部品番号で検索すれば、どの製品に使われているかがすぐに調査可能です。設計変更時の影響範囲の特定や、部品共通化によるコストダウンの検討が効率化されるでしょう。
全部門で同じ情報を共有するためにも、一元管理と最新情報の維持が不可欠です。
設計・品質管理における部品表の活用
設計・品質管理部門において部品表は、製品の正確な構成を定義し、技術情報を全部門へ伝達するための土台となるツールです。設計部品表(EBOM)は製品の骨格情報であるため、設計変更はすぐに反映させなければなりません。例えば、部品の材質変更を部品表に登録すれば、購買部門や製造部門に即時共有され手配ミスを防止します。
また、不具合発生時には部品表を遡って影響範囲を特定し、迅速な原因究明やリコール対応が可能となるため、品質保証体制の強化につながるのです。部品表は、設計の正しさと製品の安全性を担保する基盤情報と言えます。
購買・生産計画における部品表の活用
購買・生産計画部門において部品表は、「必要なものを、必要な時に、必要なだけ」調達・生産するために不可欠です。生産計画担当者は部品表を基にMRP(資材所要量計画)を実行し、製品ごとの必要部品と正確な数量を算出します。
算出された情報に基づき、購買担当者は仕入先リストや価格情報を参照して発注します。部品の欠品による生産ライン停止や、過剰在庫のリスクの低減につながるのです。正確な部品表の共有は、在庫の最適化やリードタイム短縮を実現し、サプライチェーン全体の効率化を図るうえで欠かせません。
部品表を使うメリット
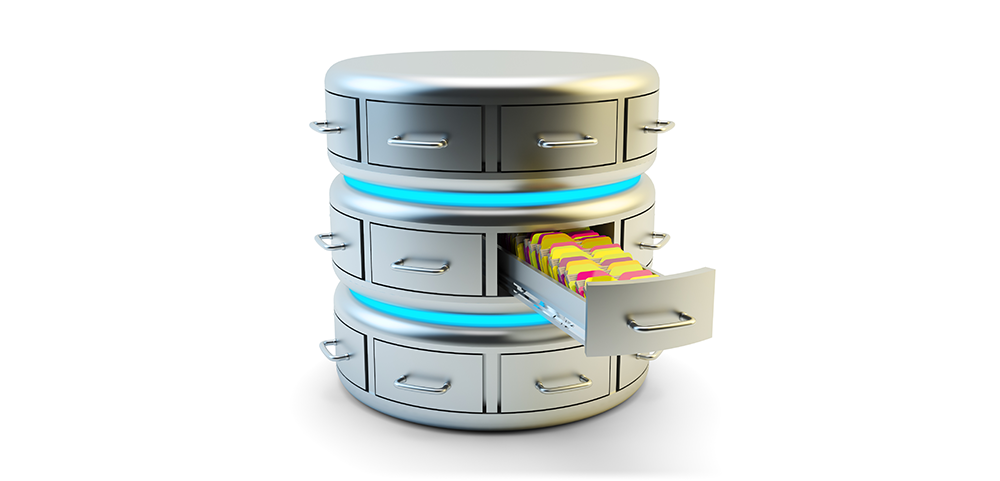
部品表の活用は、単なるリスト管理にとどまらず、情報の一元管理・共有によってものづくりの現場に多くのメリットをもたらします。
情報の一元化による部門間連携強化
製品情報を一元化し部門間の連携を強化できる点が、部品表の最大のメリットです。設計・購買・製造といった各部門が、常に同じ最新情報を参照するため、認識のズレや情報伝達の遅れを防ぎ、手配ミスなどを削減します。
例えば、設計変更を部品表に登録すれば、承認フローを経て関係部門へ即時共有されます。部品表が部門の壁を越えた「共通言語」として機能し、組織全体のコミュニケーションロスをなくし、業務効率を向上させます。
迅速な問題対応と品質向上
部品表の活用は、迅速な問題対応と製品品質の向上に役立ちます。部品情報と製品の構成が正確に紐づけられているため、不具合が発生した際に問題部品が「いつ、どの製品の、どこに」使われたのかをすぐに特定可能です。
仮に、あるロットのネジに強度不足が発覚しても、部品表があれば影響を受ける全製品リストを瞬時に抽出し、迅速なリコールや改善対策の実施が可能です。トレーサビリティを確保し、問題の拡大を最小限に食い止めるため、企業の信頼性と製品品質を守る鍵となります。
調達・生産の効率化
部品表を活用して、部品と製品の関連性が明確化できれば、部品の調達計画や生産計画を最適化し、業務全体の効率向上につながります。いつ、どの製品をいくつ生産するのかという計画に合わせ、必要な部品の種類と数量を正確に把握することが可能です。部品の過剰在庫や、逆に欠品による生産ラインの停止といったリスクを未然に防ぎます。
例えば、急な増産が決まった際も、部品表があれば必要部品リストと所要量を即座に割り出し、計画的な発注が可能です。コスト管理の精度を高め、生産リードタイムを短縮し、キャッシュフロー改善にもつながります。
人為ミスの削減
部品表を専用システムで管理すれば、手作業による入力ミスや更新漏れといった人為的なミスを削減できます。Excelなどの汎用ソフトでの管理では、担当者ごとのルールの違いやコピー&ペーストでデータの不整合や転記ミスが生じかねません。設計BOMの変更が製造BOMに反映されないといった更新漏れのリスクも生じます。
部品表システムで一元管理すれば、自動連携によって各BOMの連携ミスを防止できます。業務プロセスが標準化され、属人性も排除されるため、ヒューマンエラーの発生を根本的に減らし、データの信頼性を向上させられるのです。
部品表を使う上での注意点
部品表は便利な反面、運用を誤ると混乱やミスの原因になりかねません。ここでは、部品表を使う上で注意すべき点を3つ解説します。
データの最新性を維持する
部品表を運用する上で、データの最新性は維持しなければなりません。設計変更があったにもかかわらず部品表の更新を怠ると、古い情報に基づいて後工程の業務が進んでしまいます。誤った部品の発注や、古い仕様での製造といった致命的な手戻りや不良品の原因につながります。
「設計変更があった場合は、必ずその日のうちに部品表を更新する」といった明確な運用ルールを定め、関係者全員で徹底しましょう。部品表は「生き物」であると認識し、そのメンテナンスを怠らないことが活用の大前提となります。
複数の部品表の不整合に注意
同じ製品に対して複数の部品表が併存する場合、それらの間で情報の不整合が起きないように注意しましょう。用途が異なる設計BOM(EBOM)と製造BOM(MBOM)の内容が食い違ったままだと、深刻な問題を引き起こします。
仮に、EBOMで部品変更があっても、情報がMBOMに正しく伝わっていなければ、製造現場では旧材質の部品を使い続けてしまいかねません。対策として、EBOMを正としてMBOMを生成する仕組みや、定期的に両者の差分をチェックするプロセスを設け、BOM間の整合性を維持してください。
属人的な運用の排除
Excelや個人が管理するリストでの部品表運用は避け、専用のシステムを用いて属人性を排除しましょう。「BOMのことはAさんにしか分からない」という状況は、担当者の不在時に業務が停滞するだけでなく、ノウハウが継承されないという経営リスクにもつながります。
また、手作業による更新はミスが発生しやすく、変更履歴の追跡も困難です。PDMやPLMといった専用システムを導入して、統一されたルールでBOMを管理してください。手作業による運用から脱却し、誰でも必要な情報にアクセスできる仕組みが、安定した部品表運用につながります。
部品表の種類
部品表は、利用する部門や目的によって求められる情報が異なります。そのため、用途に応じたBOMが存在します。
設計部品表(EBOM)
設計部品表は、通称EBOM(Engineering BOM)と呼ばれます。その名の通り、設計が作成した製品の部品・ユニット構成を表にまとめたものです。最大の特徴は設計変更などを含めて最新版の構成になっていることです。
3D CADのアセンブリツリーが設計部品表に類似します。
製造部品表(MBOM)
製造部品表は、通称MBOM(Manufacturing BOM)と呼ばれます。その名の通り、製造(管理)が作成した部品表で、生産工程に準じて設計部品表を再編したものです。最大の特徴は組立工程などの要素に追加され、最新版とは時間差がある表になっていることです。
購買部品表(PBOM)
購買部品表は、通称PBOM(Purchasing BOM)と呼ばれます。購買部門や調達部門が部品を発注するために用いる部品表です。各部品の価格や発注する際の最小単位(ロットサイズ)、手配先のサプライヤーリスト、代替品の有無といった、調達に必要なデータが集約されています。購買担当者は生産計画と購買部品表を参照し、最適なタイミングとコストで部品を調達します。
サービス部品表(SBOM)
サービス部品表は、通称SBOM(Service BOM)と呼ばれ、製品出荷後のアフターサービスやメンテナンスの場面で使用される部品表です。保守・修理の際に交換が必要となる可能性のあるスペアパーツや消耗品を管理するために作成されます。製品の設計部品表とは別に、顧客へのサービス提供という独自の視点で構成されるのが特徴です。
部品管理システムの活用
製品情報の複雑化が進む中、情報を一元管理しリアルタイムで共有するには部品管理システムの活用が不可欠です。ここではシステム化の背景とメリットを解説します。
部品管理システムとは
部品管理システムとは、部門ごとに個別管理されがちなEBOMやMBOMなどの各種BOMを、一元的に管理するためのITツールです。PDM(製品データ管理)やPLM(製品ライフサイクル管理)といった、広範な製品情報を管理するシステムの中核機能として組み込まれているケースもあります。
最大の目的は、製品に関する全部門の情報を一つのマスターデータに統合する点にあります。統合により更新漏れや転記ミスを防ぎ、全部門が正しく最新の情報にアクセスできる状態を構築できるのです。
システムのメリット
部品管理システム導入の最大のメリットは、社内の誰もが必要な時に最新の部品情報へアクセスでき、部門間の情報共有と業務効率が向上する点にあります。電話やメールでの確認作業や、部品表を理解している担当者を探す手間がなくなるでしょう。
具体的には以下の効果が期待できます。
- 過去実績の検索性向上による流用設計の促進
- 変更履歴の一元管理によるトレーサビリティ確保
- 業務プロセスの標準化による入力ミスの低減
設計から製造、調達に至るまでの全体最適が実現しやすくなります。
システム導入時の注意点
システム導入を成功させるには、事前の準備が不可欠です。部品番号の採番ルールや設計変更の承認プロセスなど、これまで属人化していた業務フローを標準化し、全社で統一する必要があります。
また、既存のExcelや古いシステムからデータを移行する作業には、時間とコストがかかります。さらに、導入後の定着には、利用者全員への十分な教育と、導入目的の共有による協力体制の構築が必要です。
既存の部品表に慣れている担当者のなかには、移行に抵抗する人もいるかもしれません。一気にすべてを移行しようとせず、計画的かつ段階的に移行を進め成功体験を積んでいきましょう。
部品表に関するよくある質問・FAQ
ここでは、部品表に関するよくある質問とその回答をQ&A形式で分かりやすく解説します。
Q:部品表(BOM)と図面にある部品明細は何が違うのですか?
管理する情報の範囲と目的が異なります。図面の部品明細は、図面内の部品リストに過ぎません。一方、部品表は全社的な部品データベースであり、他の製品での流用状況や調達情報まで含みます。部品明細が「点」の情報なら、部品表はそれらをつなぐ「線」や「面」の広がりを持つ横断的な情報なのです。
Q:なぜ設計用と製造用で部品表を分ける必要があるのですか?
設計と製造ではBOMに求める情報が異なるためです。設計部品表(EBOM)は「機能・仕様」を定義し、最新の設計構成を示します。一方、製造部品表(MBOM)は「作り方」を目的とし、組立順序や工程情報を加えます。各部門の役割に最適化された情報を提供するために、目的別に部品表を分けて管理するのが一般的です。
Q:部品表はExcelで管理しても問題ないでしょうか?
小規模なら可能ですが、事業拡大と共に限界が来るでしょう。Excelの手作業は入力ミスや更新漏れが起きやすく、変更履歴の追跡も困難です。複数人での運用ではバージョン管理が煩雑になり、データの信頼性が低下して生産トラブルにつながりかねません。専用システムならこれらの課題を解決し、人為的ミスを削減できるため、早期の導入をおすすめします。
Q:部品表システムを導入する際のポイントは何ですか?
最も重要なのは、自社の業務フローに合ったシステムを選び、導入前に運用ルールを整備することです。システムは道具に過ぎないため、部品番号の採番ルールや変更プロセス等を標準化し、全社で徹底する必要があります。十分な教育や、安全に定着させるための計画的な取り組みが、導入効果を最大化させるでしょう。
Q:設計部品表と製造部品表の違いは何ですか?
設計部品表(EBOM)は、製品の機能や仕様を定義する設計部門向けのリストです。一方、製造部品表(MBOM)は、EBOMを基に組立順序や工程情報を加えて再編成した、製造部門向けのリストです。目的が「製品構成の定義」か「製造プロセスの指示」かという点が大きな違いです。
Q:EBOMとMBOMの運用はどうする?
EBOMを全ての部品情報のマスターとし、その情報に基づいてMBOMを生成・連携させるのが基本です。設計変更は即座にEBOMへ反映し、専用システムでMBOMへ自動連携させて情報の不整合を防ぎます。定期的な差分チェックも、両者の整合性を保つ上で重要です。
まとめ
本記事では、 部品表(BOM)について詳しく解説しました。部品表は、固有の「部品番号」で全部品を一元管理するのが基本であり、設計・品質管理のみならず購買・生産計画でも活用される情報基盤です。
情報の一元化による部門間連携強化をもたらし、問題対応の迅速化と品質向上にも貢献します。また、調達・生産の効率化や人為ミスの削減にもつながります。ただし、最新データの維持や複数の部品表の不整合、属人的な運用には注意が必要です。
部品表を正確に維持・管理し、部門間で共有できる体制を築いて、業務効率の向上や品質の安定、コスト競争力の強化を実現しましょう。Excel管理の限界を理解し、専用システムによる一元管理へ移行して、企業の競争力を維持してください。