炭素鋼(カーボンスチール)は、鉄と炭素の合金である鋼の一種で、合金鋼には分類されないものを指します。 汎用性が高く、機械部品から大型構造物まで幅広く用いられる炭素鋼ですが、種類が多いため最適な鋼種を選びにくいという課題があります。
本記事では、炭素鋼の基本特性と JIS 規格の 4 種(SPC・SS・S-C・SK)の違いに加え、熱処理・表面処理が性能に与える影響を解説します。
特性を把握し、要求性能に合う材料選定の参考にしてみてください。
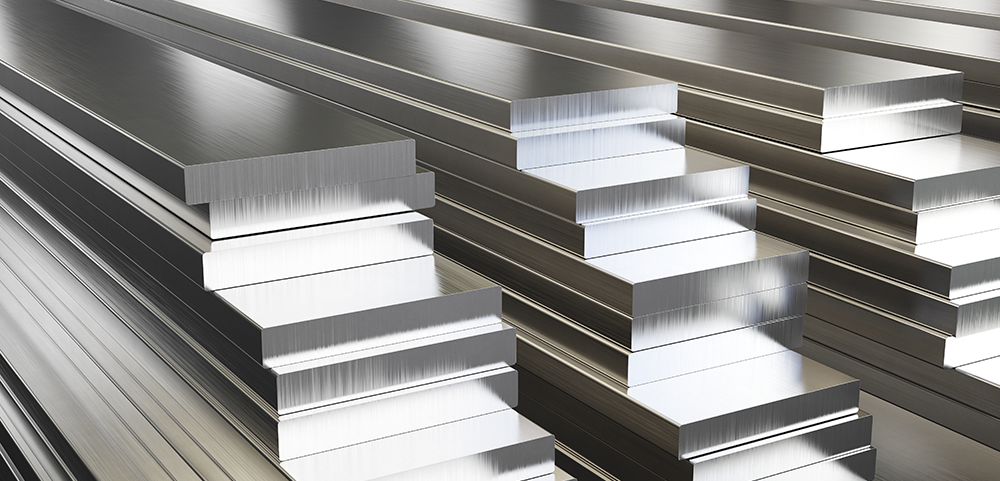
目次
炭素鋼とは
炭素鋼(カーボンスチール)とは、鉄(Fe)を主成分とし、意図的にニッケルやクロムなどの合金元素を添加していない鋼です。ステンレス鋼などの特殊鋼とは異なり、鉄と炭素(C)を基本要素とするシンプルな組成が特徴です。安価で加工しやすく、身近な機械部品から大型建築物まで広く使われています。
日本産業規格(JIS)では、炭素の含有量が0.02〜2.14%の範囲にある鉄合金を「鋼(はがね)」と定義しており、炭素鋼はこの範疇に含まれます。 炭素の含有量によって性質が変わるため、工業的には炭素量0.25%以下の場合「低炭素鋼」と呼び、0.25〜0.6%程度は「中炭素鋼」、0.6%以上は「高炭素鋼」です。これらの区分は、材料の硬さや靭性(粘り強さ)、溶接性などに直接影響し、用途に応じた使い分けの基礎となります。
炭素鋼は鉄と炭素が主成分ですが、製錬過程で必然的に含まれる微量元素も存在します。鉄鉱石からの精錬過程で不純物として硫黄(S)やリン(P)、ケイ素(Si)、マンガン(Mn)などが含まれているのが一般的です。炭素と合わせてこれらは「鋼の5元素」 と呼ばれ、炭素鋼の性質に重要な影響を与えています。
炭素鋼の特徴と注意点
熱処理の影響
炭素鋼は熱処理で硬度・強度・耐摩耗性を自在に調整でき、後加工で性能を付与しやすい材料です。
ただし、熱処理の効果は炭素の含有量に依存するため、炭素量の少ない低炭素鋼は、焼入れを行ってもほとんど硬化しません。一方で、中炭素鋼は、焼入れ・焼戻しによって硬度と引張強さを向上可能です。高炭素鋼は高い硬度を得られる一方で、靭性が低下し、溶接割れのリスクも高まるため、設計や加工には慎重な配慮が求められます。
汎用性
炭素鋼の高い汎用性は、ものづくりの現場で多く用いられる理由のひとつです。低コストで安定的に大量供給されており、板材や棒鋼、形鋼、鋼管といった多種多様な形状の規格が豊富に揃っているからです。そのため、設計者は要求寸法に合わせて材料を容易に調達できます。
加工性の面では、切削やプレス、鍛造、溶接などの工法に適応できる柔軟性を持っています。成分と熱処理条件を調整すれば、幅広い性能要求に対応可能です。自動車の車体から建築物の鉄骨、精密機械の部品に至るまで、あらゆる産業分野で標準材料として不動の地位を築いています。
侵食性
炭素鋼を用いる際の最大の課題は、侵食性、すなわち錆びやすさです。主成分である鉄は、大気中の酸素や水分と容易に反応し、酸化鉄(赤錆)を生成します。無処理のままでは短期間で腐食が進行し、部材の強度低下や外観不良を引き起こします。
浸食性を克服するため、炭素鋼部品の実用化には防錆を目的とした表面処理が不可欠です。代表的な方法として、犠牲防食作用を利用した亜鉛めっきや、溶融亜鉛メッキに加えて塗装を重ねるなどの処理が挙げられます。
コストと機械的性能に優れる炭素鋼の信頼性を担保するには、「錆とどう付き合うか」という設計段階での適切な防食対策と、運用中のメンテナンス計画にかかっています。
炭素鋼の種類
炭素鋼は、特性と用途に応じて日本産業規格(JIS)によって明確に分類されています。ここでは、4つに大別される炭素鋼の種類について、どのような特徴を持ち、どのような分野で活躍しているのかを、JIS規格の定義を交えながら具体的に見ていきましょう。
SPC材
SPC材は「Steel Plate Cold」の略で、日本語では「冷間圧延鋼板」と呼ばれます。常温で鋼材を薄く延ばしていく「冷間圧延」という製法で作られており、JIS G 3141「冷間圧延鋼板及び鋼帯」 に規定されている薄板材料です。SPC材の主な化学成分は以下のとおりです。
単位%
| 種類の記号 | C | Mn | P | S |
| SPCC | 0.15以下 | 1.00以下 | 0.100以下 | 0.035以下 |
| SPCD | 0.10以下 | 0.50以下 | 0.040以下 | 0.035以下 |
| SPCE | 0.08以下 | 0.45以下 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SPCF | 0.06以下 | 0.45以下 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SPCG | 0.02以下 | 0.25以下 | 0.020以下 | 0.020以下 |
※必要に応じて、この表以外の合金元素を添加してもよい。
SPC材の特徴は、表面が滑らかで美しい点と、板厚の精度が高い点にあります。塗装やメッキなどの表面処理後の仕上がりが重要となる自動車のボディパネルや、家電製品の筐体、スチール家具など、外観部品に多用されます。また、冷間圧延により結晶粒が微細化しているため引張強さは270N/mm2以上 まで上がるものの、降伏比が低く伸びが大きいため、深絞り加工やヘミング曲げに適します。
SPCC(一般用)、SPCD(絞り用)、SPCE(深絞り用)などの種類があり、プレス加工の難易度に応じて使い分け可能です。硬度や強度は低いものの、優れた加工性で大量生産部品を支える材料です。
SS材
SS材は「Steel Structure」の略称で、「一般構造用圧延鋼材」を指します。JIS G 3101に規定されており、建築物や橋梁、船舶、車両などの骨格となる構造部材として広く使用されている炭素鋼です。主な化学成分は以下のとおりです。
単位%
| 種類の記号 | C | Mn | P | S |
| SS330 | – | – | 0.050以下 | 0.050以下 |
| SS400 | ||||
| SS490 | ||||
| SS540 | 0.30以下 | 1.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 |
※必要に応じて、この表以外の合金元素を添加してもよい。
SS材は、「引張強さ」の下限値が保証されている点が最大の特徴です。たとえば、「SS400」という記号は、引張強さが400N/mmであることを示しています。
また、化学成分の規定は緩やかですが、溶接性や加工性にも優れており、H形鋼や山形鋼、鋼板などさまざまな形状で安価に流通しています。熱処理による硬化は期待できないものの、加工後の変形が少なく、大規模な構造物を効率的かつ経済的に建設するうえで不可欠な材料です。
S-C材
S-C材は「Steel Carbon」を意味し、「機械構造用炭素鋼鋼材」としてJIS G 4051に規定される材料です。代表的な化学成分は以下のとおりです。
単位%
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Ni+Cr |
| S30C | 0.27〜0.33 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.30以下 | 0.35以下 |
| S45C | 0.42〜0.48 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.30以下 | 0.35以下 |
| S50C | 0.47〜0.53 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.30以下 | 0.35以下 |
この表に規定されていない元素は、溶鋼を仕上げる目的以外に意図的に添加してはならない。
SS材が「最低限の強度」を保証するのに対し、S-C材は炭素含有量をはじめとする化学成分が厳密に管理されているのが特徴です。代表的なのがS45Cで、この「45」は炭素含有量が約0.45%であることを示します。熱処理によって強度と耐摩耗性を大幅に向上できるため、歯車(ギア)や軸(シャフト)、クランクシャフト、ボルトなど、高い負荷がかかる機械の動力伝達部品や締結部品に広く採用されています。
SK材
SK材は「Steel Kougu(Tool)」の頭文字を取ったもので、「炭素工具鋼鋼材」を指します。JIS G 4401に規定されており、工具や刃物を製造するために特化した炭素鋼です。代表的なSK材の化学成分は以下のとおりです。
単位%
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S |
| SK105 | 1.00〜1.10 | 0.10〜0.35 | 0.10〜0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SK95 | 0.90〜1.00 | 0.10〜0.35 | 0.10〜0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SK85 | 0.80〜0.90 | 0.10〜0.35 | 0.10〜0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 |
炭素含有量が0.6%以上と高く、焼入れ処理によってマルテンサイトという硬い組織に変態します。高い硬度を誇るため、優れた切削能力や耐摩耗性を発揮します。ドライバーやレンチといった手工具、ドリルやエンドミルの刃先、プレス用の金型など、他の材料を削ったり、変形させたりするための「道具」として使用されるのが特徴です。
ただし、非常に硬い反面、靭性(粘り強さ)は低く、衝撃によって欠けやすいという側面も持つため、用途に応じた適切な熱処理としなやかさを持たせる焼戻しが重要になります。
炭素鋼の用途
以下に炭素鋼の用途をカテゴリ別にまとめます。
| 用途カテゴリ | 主に用いられる鋼種 | 典型的な部品・構造例 | 選定ポイント |
| 建築・土木構造物 | SS材(SS400など) | H形鋼、橋桁、鉄塔、建築物の骨組 | ・溶接しやすく大量調達が容易
・屋外では防錆処理が必須 |
| 産業機械・プラント機器 | SS材、S-C材(S45C、S50C) | 機械フレーム、コンベア、歯車、軸 | ・骨格にはコスト重視のSS材
・強度や耐摩耗性が必要な部品には熱処理前提のS-C材 |
| 自動車・各種乗り物 | SPC材、SS材、S-C材、SK系 | ボディパネル、シャーシ、ギア、シャフト、板ばね | ・軽量化と耐久性の両立が求められる
・部位ごとにプレス性、強度、ばね性など最適な鋼種を使い分ける |
| 工具・刃物類 | SK材(SK85など) | ドリル、タップ、のこ刃、金型ポンチ | 焼入れにより高硬度・耐摩耗性が得られるが、靭性は低い |
| 薄板プレス製品 | SPC材(SPCC、SPCD) | 家電筐体、配電盤、ブラケット | ・表面が平滑で深絞り性に優れる
・大量生産に向き、塗装やメッキが前提 |
| 日用品・汎用部品 | SS材、SPC材 | クリップ、釘、ビス、スチール棚 | ・低コストで入手しやすい
・簡易的なメッキや塗装で防錆して手軽に使用される |
このように、炭素鋼はそれぞれの特性を活かして、適材適所で社会を支える基本的な材料として機能しています。
炭素鋼でよく使われる表面処理
炭素鋼部品を使用する際には防錆・防食のための表面処理が不可欠です。以下に炭素鋼に対して一般的によく施される表面処理の代表例を紹介します。
黒染め(四三酸化鉄被膜処理)
黒染めは、薬品で表面に黒錆の皮膜を形成する防錆処理です。最大の特徴は、皮膜が1〜2μmと極めて薄く、部品の寸法変化がほとんどない点です。精密な寸法が求められる機械部品や治具、工具類に広く採用されています。光の反射を抑える効果もあり、カメラ部品にも利用されます。低コストで防錆と落ち着いた黒色の外観を両立できる、費用対効果の高い方法です。
亜鉛メッキ
亜鉛メッキは、鉄の身代わりとなって亜鉛が先に錆びる「犠牲防食作用」により、母材を強力に保護する表面処理です。屋外のガードレールや建築資材など、常に風雨に晒される部材に不可欠な処理となっています。比較的安価で高い防錆効果が得られるため、社会インフラを支える多くの鋼構造物で採用されています。
ニッケルメッキ
ニッケルメッキは、優れた耐食性と美しい金属光沢を両立できる表面処理です。緻密な皮膜で錆を防ぎつつ、銀白色の美しい外観を与えるため、水道の蛇口のような装飾部品に多用されます。特に「無電解ニッケルメッキ」は、複雑な形状の部品でも隅々まで均一な厚さでメッキでき、寸法精度を高く保てるため、精密機械の機能部品にも採用され、性能向上に貢献しています。
クロムメッキ
クロムメッキは、トップクラスの硬度で炭素鋼に優れた耐摩耗性を与える処理です。非常に硬く滑らかな皮膜は、部品同士が激しくこすれ合う過酷な環境から摩耗や傷を防ぎます。その特性から、油圧シリンダーのロッドなど、摺動部品の摩耗を防いで機械の性能と寿命を向上させます。輝かしい光沢から、自動車のエンブレムなど装飾目的でも利用される高性能な表面処理です。
その他の処理
これまで紹介した処理の他にも、用途に応じて多様な表面改質が行われます。一般的なのが、塗料の膜で物理的に保護する塗装です。下地としてリン酸塩被膜処理(パーカー処理)を施し、塗膜の密着性を飛躍的に高めます。歯車など極めて高い表面硬度が求められる場合には、炭素や窒素を表面に浸透させて硬化させる浸炭や窒化といった熱処理で、耐摩耗性の向上が可能です。
SS400とは(SS材)
SS400は一般構造用圧延鋼材と呼ばれるSS材(Structural Steel)の一種です。
SS材とは名前のとおり、一般的な構造物の材料として圧延で作られた鋼で、SS材の名前は「SS」の記号と、後に続く3ケタの数字で表されます。古くはSS41と表記されていました。3ケタの数字は材料の引っ張り強さを表しており、SS400であれば、引張強さが400N/mm2以上の構造用鋼という意味になります。 SS材にはSS400以外にもSS300やSS490のほかSS540などの種類がありますが、その中でも最も広く使われているのがSS400です。
SS400の特徴
SS400はほかの金属材料に比べると安価で入手しやすいのが特徴です。
溶接や切削などの加工がしやすいという特徴もあります。また板材の状態での流通も多く、板金加工やレーザーカットなども行えます。しかし、焼き入れはできません。また錆びやすい素材なのでめっきや黒染めなどの防錆処理が必要です。
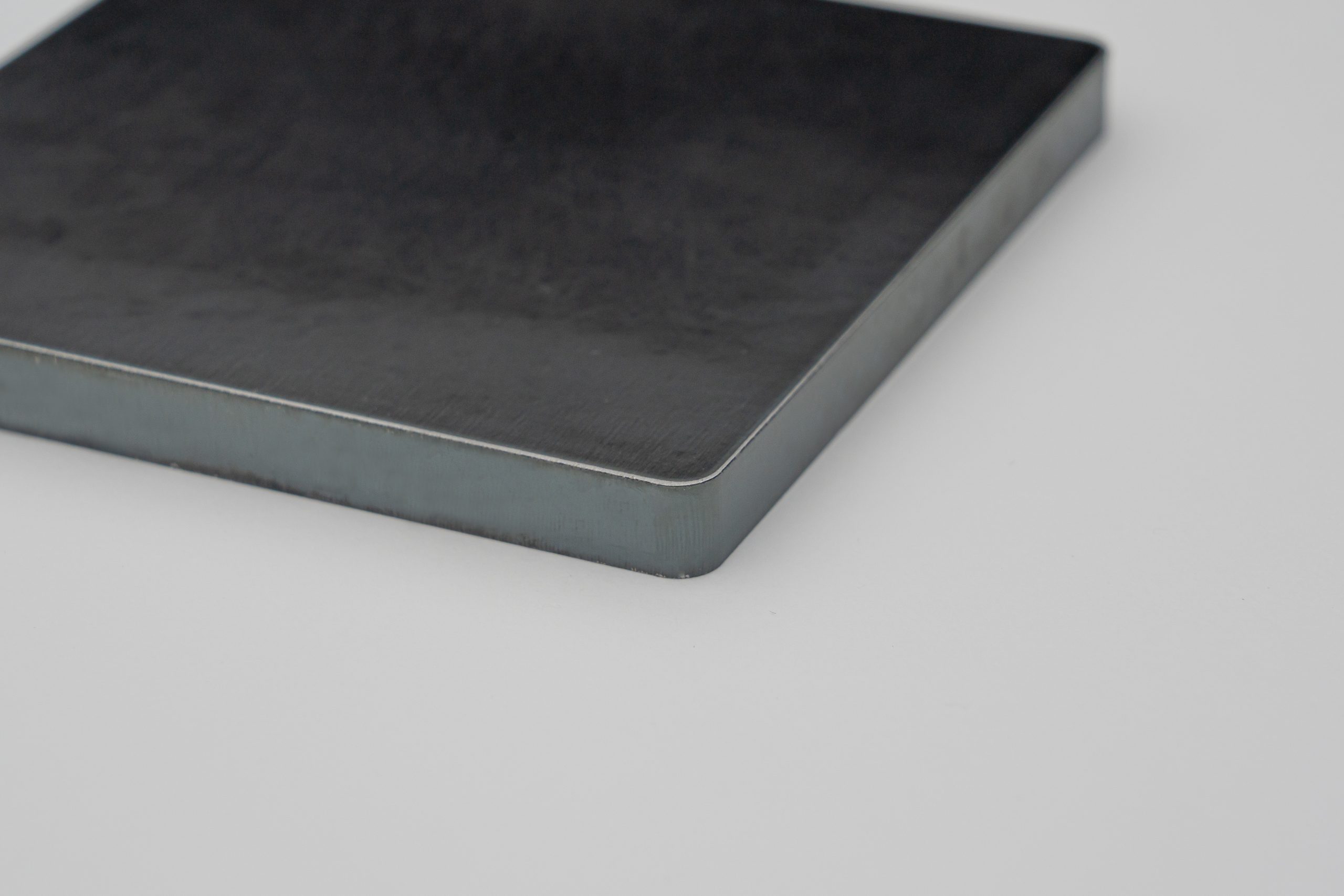
SS400の用途
SS400は橋や船などの構造材に使われるほか、大型の機械や車両など、機械分野から建築分野まで幅広く使われています。鉄や鋼で何かを作ろうと思った際に、設計者が一番最初に思い浮かべる材料といっても過言ではありません。SS400は、それくらい広く、一般的に使用されている素材です。
メリット
- 安価で入手しやすい
- 溶接しやすい
- 板金や切削などの加工にも向いている
- 汎用性が非常に高い
広く流通している汎用素材ですので、ほかの金属素材に比べて値段が安く入手しやすい素材です。ステンレスなどに比べると軟らかいため、切削や板金などの加工もしやすく、さまざまな用途で利用できます。炭素量が低く、熱による影響を受けにくいので溶接にも向いています。しかし板厚が25mm以上になるなど、厚い素材を溶接したい場合にはSS400ではなくSM材などの溶接用の材料を使用したほうがいいでしょう。
デメリット
- 焼き入れができない
- 鉄鋼材料の中では軟らかい
- 錆びやすいため、めっきや塗装などの腐食対策が必要
SS400は非常に一般的な材料であるため、鉄鋼材料としては特別に強い材料ではありません。より強い材料が必要な場合などはほかの材料も検討する必要があります。また炭素量が低く焼き入れもできないため、表面のみの硬さを得るような加工もできません。また錆びやすい素材のため、めっきや塗装、黒皮(酸化被膜)での保護が必要です。
よく使われる表面処理
SS400は錆びやすいため、ニッケルめっきやクロムめっきなどの表面処理を施すケースが多いです。橋梁など、私たちの生活で目にするSS材は、めっき処理したものをさらに塗装しているケースがほとんどです。また水のかからない場所など、それほど高い耐腐食性を要求されない場合には、黒皮(酸化被膜)処理されたものを使うケースもあります。建設工事現場の出入り口や地面の上に敷かれている黒っぽい鋼材が、黒皮処理されたSS400です。
表面処理の一覧
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め):薬品を用いて鉄の表面を酸化させ、四酸化三鉄(Fe3O4)の被膜で覆います。腐食を防止します。
- 無電解ニッケルめっき:化学的還元作用によりニッケルリンめっきを施します。熱処理とあわせて行うことで、表面の硬度を上げ、耐摩耗性を向上させます。
- 硬質クロムめっき:装飾クロムめっきよりも厚いクロムめっきです。耐摩耗性や摺動性が向上します。
- 三価クロメート:めっきの品質向上のため、めっきの後処理として行われる処理です。主に電気亜鉛めっきに使用されます。
S45Cとは(S-C材)
S45Cは機械構造用炭素鋼鋼材と呼ばれるSC材(Steel Carbon)の一種です。S45Cもまた、機械材料として非常に多く使われる素材です。
SC材は「SC」の記号とその後に続く2桁の数字で種類が表記されます。数字の部分は材料の炭素含有量を意味し、S45Cであれば、0.45%の炭素が含まれていることになります。以前はS450Cと表記されていたため、古い図面などではS450Cという記載を見つけられるかもしれません。
S45Cの特徴
S45CはSS400と並んで、非常によく使用される材料です。またSC材の中では最もポピュラーな素材として知られています。そのため比較的安価で入手しやすく、さまざまな場所に使用されています。
焼き入れなどの熱処理によって耐摩耗性や硬さなどをコントロールできるため、歯車のような耐久性を求める機械部品に特に多く使われます。一方で錆びやすいため、油の塗布や塗装などの防錆処理が必要になります。
S45Cの用途
S45Cは機械の部品、とくに機械の内側にある部品に多く使用されています。
例えば自動車のエンジン周辺部品やギアのほか、プーリーやブラケットのような標準的な機械部品にも使われます。鉄系材料で何かを作ろうと考えた場合、強度をあまり必要としない場合にはSS400、強度や耐久性が必要な場合にはS45Cがまず最初の材料の候補に挙がるといっても過言ではありません。それほどまでに一般的な機械部品材料として使用されている材料です。
メリット
- 熱処理により強度を与えられる
- 切削加工は熱処理前であればやりやすい
- 汎用性が高い
広く流通している汎用素材ですので、ほかの金属素材に比べて値段が安く入手しやすい素材です。焼き入れ前であれば、切削加工もしやすいので、歯車などを作る際には切削加工後に熱処理を行うのが一般的です。一方で研削加工については、切削加工の後に熱処理を行い、その後に寸法調整などのために研削を行うのが一般的です。
デメリット
- 溶接には向かない
- 板金にはあまり使われない
- 錆びやすいため表面処理などが必要
S45Cは熱処理に向いている素材です。つまり熱により性質を変えやすいため、逆に熱を使う溶接にはあまり向きません。
使われる表面処理
表面処理の選び方はSS400と同じです。
S45Cは炭素鋼であるため、焼き入れや焼き戻しのほか、焼きならしや焼きなましなど、一般的な熱処理が多く行われます。一方で合金鋼ほどには焼き入れ性が高くないため、あまり深くまで焼き入れを行うことはできません。歯車などのように、表面の耐久性が強く求められる場合には、高周波焼き入れを行うことも多くあります。
S50Cとは(S-C材)
S50CはS45Cと同じ機械構造用炭素鋼鋼材、SC材の一種です。
S50Cには0.50%の炭素が含まれています。前述の通り、鉄は含まれる炭素の量が多くなればなるほど硬くなる性質をもっています。そのためS50CはS45Cよりも硬くなりますが、その分、やや脆くなってしまいます。また材料のコストもSS400やS45Cに比べると高くなります。
S50Cの特徴
S50CもS45Cと同様に、機械部品などに多く使用される材料です。しかしS50CはSC材の中でも炭素量が多い素材に分類されます。硬さや引っ張り強さだけでなく、耐摩耗性などもS45Cよりも高くなりますので、より高い強度が求められる部品などに使用されます。
S50Cも熱処理が可能です。また耐腐食性は低いので、防錆処理が必要です。
S50Cよりも炭素量の多いSC材としてS55Cが挙げられます。S55CはS50Cよりもさらに硬く、耐摩耗性などに優れる素材です。S50Cとの使い分けは、素材の強度のほか、流通している材料形状などによって行われます。
S50Cのメリットとデメリット、よく使われる表面処理は、S45CやC55Cと同じです。
S50Cの用途
S50Cは機械の部品の中でも比較的強度を要する部品に多く使用されます。
例えばシャフトやボルトナットのような、強い力のかかりやすい部品や、金型のように耐久性が求められる装置に使用されています。
SS400・S45C・S50Cの機械的、物理的性質
ここからは、これまでに解説してきたSS400とS45CおよびS50Cのスペックについてまとめていきます。設計などの際には、このような数値に着目して計算をすすめていきます。
機械的性質
SS400とS45CおよびS50Cの機械的性質はJISにより下表のように定められています。
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
| 種類 | 材質記号 | 熱処理(℃) | 機械的性質の代表値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張り強さ (N/mm2) |
耐力 (N/mm2) |
伸び | 硬度 | ||||
| 構造用鋼 | SS400 | − | 400~510 | 215以上 | 21%以上 | − | |
| 炭素鋼 | S45C | 焼きならし | 810~860 空冷 |
570以上 | 345以上 | 20以上 | 167~229HBW |
| 焼鈍 | 約800 炉冷 |
− | − | − | 137~170HBW | ||
| 焼き入れ | 810~860 水冷 |
690以上 | 490以上 | 17以上 | 201~269HBW | ||
| 焼き戻し | 550~650 急冷 |
||||||
| S50C | 焼きならし | 810~860 空冷 |
610以上 | 365以上 | 18%以上 | 179~235HBW | |
| 焼鈍 | 約800 炉冷 |
− | − | − | 143~187HBW | ||
| 焼き入れ | 810~860 水冷 |
740以上 | 540以上 | 15%以上 | 212~277HBW | ||
| 焼き戻し | 550~650 急冷 |
||||||
物理的性質
SS400とS45CおよびS50Cの物理的性質はJISにより下表のように定められています。S45CとS50Cの物理的性質には大きな違いはありません。
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
SS400の物理的性質
| 物理的性質 | 縦弾性係数(ヤング率)[GPa] | 横弾性係数[GPa] | ポアソン比(常温) | 密度[g/cm3] | 比重 | 融点[℃] | 熱伝導率[W/(m・K)] | 熱膨張係数[10-6/K] | 固有抵抗[10-8Ω・m] | 比熱[J/(kg・K)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物性値 | 205~206 | 79~82 | 0.27~0.29 | 7.84~7.86 | 7.84~7.86 | 1660~1770 | 44~60 | 10.7~11.6 | 13.3~19.7 | 0.474~0.494 |
S50Cの物理的性質
| 融点 | 密度 (g/cm³) |
ヤング率 (縦弾性係数) |
剛性率 (横弾性係数) |
ポアソン比 | 線膨張率 (ppm/K) |
定圧比熱 (J/kg・K) |
熱伝導率 (W/m・K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPa | GPa | ||||||
| 約1,660〜1,680℃ | 7.84 | 205 | 82 | 0.25 | 11.7 | 489〜494 | 44 |
SS400・S45C・S50Cの標準寸法
炭素鋼で多く流通している素材の選び方はこちらをご覧ください。
今回の記事で紹介してきた材料の標準寸法は下記の通りとなります。
| 種類 | 材料記号 | 形状 | 単位 | 標準寸法 |
|---|---|---|---|---|
| 一般構造用 圧延鋼材 |
SS400 | 平鋼 | t | 6,9,12,13,14,16,19,22,25,28,30,32,35,38,40, 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 |
| 角鋼 | □ | 9,13,16,19,22,25,32,38,44,50,65,75,90,100 | ||
| ミガキ棒鋼 (冷間引抜) |
SS400D | 平鋼 | t | 2, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,28,30,32,34, 35,36,38,40,42,44,45,50,55,60,65,70,75,80, 85,90,100,110,120,130 |
| 六角鋼 | 対辺H | 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,21,22,23, 24,26,27,29,30,32,35,36,38,41,46,50,54, 55,58,60,63,65,67,70,71,75,77,80,85,90,95, 100,115 |
||
| 丸棒 | D | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,48,50, 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110, 115,120,130,140,150,160,170,180,190,200 |
||
| 機械構造用 炭素鋼鋼材 |
S45C-D (ミガキ) |
丸棒 | D | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 6,7,8,9, 9.5, 10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,40, 42,44,45,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85, 90,95,100,105,110,115,120,125,130 |
| S45C | 平鋼 | t | 3, 4.5, 5,6,8,9,10,12,16,19,22,25,30,32,38,50 | |
| S50C | 平鋼 | t | 6, 9.5, 12.7, 13,16,19,22,25,27,32,38, 45,50,55,65,75,85,95,105,115,125,135, 145,155,(165),(175),(185),(205) |
|
| 角鋼 | □ | 12.7, 13,16,19,25,28,32,38,44,50,55, 65,75,90,100,110,120,130,155 |
しかしこの標準寸法はJISによって定められているものであり、実際の流通状況を表すものではありません。また流通状況は時事情勢によっても変動します。そのため、材料の形状と寸法については、材料メーカーのパンフレットなどで確認してください。
まとめ
炭素鋼とは、鉄(Fe)を主成分とし、合金元素を大きく添加せず、炭素(C)を主な強化元素とする鋼材の総称です。合金鋼や特殊鋼とは区別され、汎用性が高く、機械部品から構造材まで広く使われます。
炭素鋼の性質・性能としては、炭素含有量により靭性・硬さ・強度が変化し、熱処理によって性能制御しやすい点が特徴です。ただし、錆びやすく耐食性には注意が必要です。
SS400とは、JIS G 3101 に規定される「一般構造用圧延鋼材」で、構造用鋼材として広く使われる代表的な炭素鋼種です。
SS400は、引張強さ 400~510 N/mm² 程度、降伏強度下限 215 N/mm²、伸び率21%以上と定められ、加工性・溶接性が良好でコストも低めなため、フレームや架台に使用されることが多いです。ただし硬化処理は難しく、耐食性を補う表面処理が必要です。
S45Cとは、JIS G 4051 の「機械構造用炭素鋼」で、炭素含有率 0.42~0.48 % 程度の中炭素鋼です。
S45Cは、熱処理(焼入れ・焼戻し)により硬さ・耐摩耗性を向上できる点が強みです。引張強度は熱処理後で 810~860 N/mm² 程度、降伏強度・硬さも高まり、機械要素部品(軸・ギア・ボルトなど)に適用されます。
S50Cは、S45C より炭素含有量を高めた材料で、より高硬度・耐摩耗性を追求した機械部品向きの高炭素鋼です。
関連記事
亜鉛メッキ鋼板(SECCとSGCC)の用途・種類・特徴を解説
圧延鋼板の用途・種類・特徴 SPHC(熱間圧延鋼板) 、SPCC(冷間圧延鋼板)
焼き入れ不要の高硬度鋼材NAK材をご存知ですか?切削プレートの素材紹介











