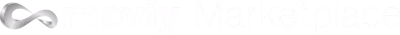金型材料として有名なSKD61は、高温環境下でも優れた性能を発揮する熱間ダイス鋼です。
本記事では、SKD61の定義や規格、特性・特徴について解説し、具体的な用途や加工方法での注意点についてまとめます。設計・開発や調達の担当者が材料選定に役立てられるよう、SKD61の長所と短所、他の鋼材との比較などをわかりやすくまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。
SKD61とは?
ここではSKD61の定義や規格上の位置づけ、代表的な使用分野について説明します。
SKD61の定義と規格
SKD61は日本産業規格(JIS G 4404)に規定された熱間ダイス鋼の一種です。名称の「SKD」はそれぞれ Steel(鋼)・Kogu(工具)・Die(ダイス)を意味し、末尾の「61」は合金成分グレードを示します。
アメリカの規格ではAISI H13に相当し、ドイツDINでは1.2344と同等の材質です。SKD61の化学成分は、JIS G 4404で以下のように規定されています。
単位%
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | W | V | Co |
| 0.35〜0.42 | 0.80〜1.20 | 0.25〜0.50 | 0.030以下 | 0.020以下 | ※ | 4.80〜5.50 | 1.00〜1.50 | ※ | 0.80〜1.15 | ※ |
※意図的に添加してはならない。
成分には炭素鋼をベースに、高温強度や焼入れ性を高めるクロム(Cr)、モリブデン(Mo)、靱性を向上させるバナジウム(V)などが添加されており、高温強度や耐摩耗性、靱性(ねばり強さ)をバランス良く高めています。
代表的な使用分野(金型・鋳造など)
SKD61は高温環境下で使用される金型や工具に広く使われている材料です。代表例として、アルミニウムやマグネシウムのダイカスト(金型鋳造)や熱間鍛造用の金型が挙げられます。
ダイカスト型では、溶融金属を高圧で射出するため金型が繰り返し高温にさらされるものの、SKD61は過酷な条件下でも熱疲労や熱亀裂に強い耐性を持ちます。
また、自動車や航空機産業で使われる鍛造金型にも採用され、急激な温度変化にも耐える特性が評価されている材料です。さらにプラスチック射出成形金型や押出し金型、ホットパンチ(金属の熱間打ち抜き工具)など、高温もしくは高負荷の加工が行われる分野で幅広く利用されています。
SKD61の特性
優れた機械的特性と物理的・化学的特性は、SKD61が選ばれる最大の理由です。ここでは、SKD61の主要な特性について見ていきましょう。
機械的特性(強度・靱性・耐摩耗性)
SKD61は熱処理(焼入れ・焼戻し)によって硬さと強度が向上する鋼材です。適切な熱処理を施せば、耐摩耗性に優れた表面を実現できます。
JIS G 4404では、焼入れ・焼戻し後の硬さの基準が定められています。
| 焼入れ(℃) | 焼戻し(℃) | 焼入焼戻し硬さ(HV) |
| 1020 空冷 | 550 空冷 | 513 |
さらに、硬さと同時に高い靱性を備えている点も強みです。SKD61は衝撃荷重にも耐える強靭さを有しており、激しい加工条件でも割れや欠けが生じにくい特徴があります。
また、耐摩耗性については、同じ工具鋼のSKD11ほど極端に高くはないものの、十分高い水準にあります。硬度と靱性のバランスが良いため、過酷な条件下で長期間使用しても大きな摩耗や破損が起きにくいのがSKD61の強みと言えるでしょう。
物理的・化学的特性(耐熱性・耐食性・熱伝導性)
SKD61の主な物理的特性は以下のとおりです。
| 比重 | 熱膨張係数 | 縦弾性係数(ヤング率) | |
| 7.75 | 10.8×10–6/℃ | 205,800 N/mm² | 21,000 Kgf/mm² |
SKD61の最大の特徴は、高温環境下での強さの維持にあります。通常の工具鋼は高温になると硬さや強度が低下しますが、SKD61は摂氏300℃〜500℃程度の高温でも硬度低下が少なく、熱による劣化に強い素材です。これは添加されているMoやV元素によって、高温での組織安定性や耐熱疲労性が高められているためです。
熱衝撃(急激な加熱冷却)に対する耐性も優秀で、温度変化の激しいダイカスト工程でも亀裂が発生しにくい特性を持ちます。
一方、耐食性については、Cr含有量が約5%とステンレス鋼ほど高くないため錆びやすい部類に入ります。そのため、防錆油の塗布や表面処理(メッキ)による防錆対策が欠かせません。
SKD61のメリット
耐熱衝撃性に優れる
SKD61の大きなメリットのひとつが、熱衝撃に対する優れた耐性です。モリブデンを多く含む配合設計により、高温下での引張強さ(強度)が高く保たれるのが特徴です。
さらに、バナジウムの添加によって高温時の靱性が確保され、急熱急冷による熱亀裂(ヒートチェック)が発生しにくい材料となっています。結果として金型の寿命延長につながり、保守交換の頻度を減らせます。
高温下で酷使される部品でも安定した強度と寸法を維持できるため、信頼性の高い製造プロセスに貢献します。
幅広い加工適性
SKD61はさまざまな加工プロセスに対応しやすい点もメリットです。まず、未熱処理の状態(焼なまし材)では比較的切削性が良好であり、フライスや旋盤による切削加工で所定の形状に削り出し可能です。
硬度が高い鋼材ではあるものの、焼なまし状態ではHBW229以下に軟化しており、適切な切削工具と条件を選べば加工できます。また、SKD61は熱処理後も完全な空冷で硬化する鋼種で、大型部品でも均一に硬度を得やすい性質があります。
各種の表面処理との相性も良く、用途に応じた追加処理を施せば性能をカスタマイズ可能です。
コストと性能のバランスの良さ
SKD61は性能とコストのバランスに優れた鋼材です。合金工具鋼の中では古くから標準的に使われているため流通量が多く、入手しやすい材料でもあります。需要と供給が安定していることから価格も比較的安定しており、特殊鋼の中では極端に高価というわけではありません。
一方で性能面は前述の通り高く、コストパフォーマンスが良好です。SKD61は加工性が比較的良く靱性が高いため破損しにくく、長期的に見た運用コストを抑えやすいという利点があります。
初期材質コストや加工費は必要でも、長寿命化による交換頻度低減やトラブル防止でトータルコストの低減につながりやすいのです。
SKD61のデメリット
高硬度ゆえの加工難度
SKD61は硬度が高く耐摩耗性に優れる一方で、加工のしにくさという課題を持ちます。特に焼入れ・焼戻し後の硬化処理を経た状態では切削加工が困難です。
硬化後の硬度HV513にもなるSKD61は、一般的な切削工具では刃が立たないほど固く、加工中に工具摩耗が激しく進行します。研削盤による研磨加工であっても、硬い分だけ加工に時間がかかり、生産性に影響を及ぼしかねません。
また、SKD61は所定の機械的性質を得るために焼入れ温度が1020℃前後と高温が必要であり、熱処理設備や技術が要求される点も難しさの一つです。熱処理前の焼なまし材の段階でできるだけ最終形状に近づけて加工を済ませ、仕上げの研削代を最小限に留めましょう。
熱処理による寸法変化のリスク
SKD61に限らず工具鋼全般に言えることですが、焼入れによってマルテンサイト組織に変態し硬化する際、素材内部に応力が生じるため体積変化やひずみが避けられません。SKD61の場合も熱処理後に若干の縮みや変形が起こりやすく、精密な寸法が要求される部品では問題となる場合があります。
特に大きな金型部品などでは、部分的な冷却速度の差からひずみ量が不均一になりがちです。設計段階で機械加工の仕上げしろ(ひずみ取り代)を設けておき、熱処理後に最終研磨で寸法を整えるのが一般的です。
対策を講じないままでは、思わぬ寸法狂いやひずみが製品不良を招く恐れがあるため、SKD61の熱処理工程は細心の注意が必要です。
SKD61の用途
SKD61の主な用途を紹介します。
ダイカスト金型
SKD61は、ダイカスト(高圧鋳造)金型に広く採用されている材料です。
アルミニウムや亜鉛などの溶融金属を金型に射出するダイカスト工程では、金型表面が数百℃に達し、その後冷却されるサイクルを繰り返します。SKD61は、過酷な条件下でも高温強度を維持し、熱疲労に強いため、自動車エンジン部品や通信機器筐体などのダイカスト金型に標準的に使用されます。
適切な熱処理と表面処理を施せば、何千ショットもの射出に耐える高耐久性が実現可能です。耐熱衝撃性によりヒートチェックの発生を抑え、製品の寸法精度を長期間安定させるという利点もあります。
押出し金型
SKD61は、押出し成形、特にアルミニウム材の押出しにおいて重要な材料です。500℃前後の高温・高圧環境で使用される押出しダイスは、摩耗と熱応力に耐える必要があり、SKD61はこれらの条件に耐えるように設計されています。
SKD61製の押出し金型は、高温での強度低下が少なく形状を維持するため、製品寸法の安定に役立ちます。また、適度な靭性により、押出し時の衝撃にも耐え、長時間の連続生産に適している点も強みです。
アルミサッシやヒートシンクなどの形材を製造する押出しラインにおいて、ダイス交換頻度を減らし、生産効率を高める効果が期待できます。
鍛造金型
SKD61は、自動車部品や航空機部品の製造に用いられる熱間鍛造金型に活用されています。
熱間鍛造は鋼塊を約1000℃に加熱し、プレス機で成形する過酷な環境です。SKD61は、高温下での強靭さと耐摩耗性、衝撃荷重に対する靱性に強みをもつ材料です。したがって、クランクシャフトやギアブランクなどのダイス材として金型の軟化や破損リスクを低減し、繰り返し成形に耐えられます。
SKD61は、数百〜数千トンもの圧力がかかる熱間鍛造の負担に耐えるための鋼材と言えます。
耐熱部品(航空機・自動車など)
SKD61は金型だけでなく、航空機エンジンや自動車の排気系など、500℃程度の高温環境で使用される機械部品にも利用されます。
高温強度と耐熱疲労性が必要な射出成形機のシリンダーやノズルなどにも適しており、400〜500℃程度までの高温部品においては、高価な超合金の代替として経済的なメリットも提供可能です。
SKD61の加工方法と注意点
次にSKD61の加工種類と注意点についてまとめます。
熱処理(焼入れ・焼戻しの最適条件)
SKD61の性能は熱処理に大きく左右されます。
一般的な熱処理の流れは、まず焼なましをして素材を軟化させ加工しやすくし、その後に焼入れ・焼戻しを行って所要の硬さと靱性を付与するという順序です。
焼なましは820〜870℃で行われます。焼入れは約1020℃という高温まで加熱した後、空冷によって行います。このままでは内部応力が大きく脆い状態なので、高温焼戻しを2回程度行います。焼戻し温度は550℃で、その後、空冷します。
熱処理の際は、ひずみ対策と表面品質に注意が必要で、真空炉の使用や徐冷といった工夫が求められます。
切削加工(工具摩耗・切削条件)
SKD61の切削加工は、基本的に熱処理前の焼なまし材に対して行います。
焼なまし材でも硬度はHBW229以下と比較的高硬度ですが、超硬工具やコーティング工具を使用し、低めの切削速度と十分な切削油、高剛性の工作機械と工具ホルダーを用いれば、フライス・旋削・穴あけ加工が可能です。工具摩耗が激しい場合は、セラミック工具やCBN工具も検討されます。
高硬度材の最終加工には放電加工(EDM)が有効です。SKD61は難削材ですが、軟らかい段階での粗加工と硬化後の仕上げという手順を踏めば精密加工が可能です。
研磨加工(表面仕上げ・割れ防止のポイント)
SKD61の最終仕上げには研削盤による研磨加工が用いられます。
熱処理後のSKD61は非常に硬いため、適切な砥石を選定し、こまめにドレッシングを行うことが重要です。研削中の砥石の目詰まりや研削焼けを防ぐため、十分な冷却液供給と適切な送り速度・切込み設定が必要です。
高品質・高信頼性の仕上げには、「熱と応力を残さない」ことが求められます。
他の合金鋼との比較
ここでは、よく比較対象となるSKD11(冷間ダイス鋼)との違いや、ステンレス鋼(SUS系)との特性差について解説します。
SKD61とSKD11の違い(耐摩耗性 vs 耐熱性)
工具鋼として広く使われているSKD61とSKD11は、それぞれ「熱間ダイス鋼」と「冷間ダイス鋼」に分類され、性能特性や適する用途が異なります。
SKD11は高炭素・高クロム成分によりSKD61よりも硬度と耐摩耗性に優れている一方で、200℃を超えると急激に硬度・強度が低下します。一方、SKD61は靱性や高温下での強度維持に優れ、MoやVの含有により300℃近くでも強度を保てる点が強みです。
このため、常温〜中温域での耐摩耗性と長寿命を求めるならSKD11、繰り返し高温にさらされる環境での耐久性を求めるならSKD61が適しています。
SKD11の特性や用途に関する詳しい情報は、こちらの記事もご参照ください。
SKD11とは?特性・用途・加工時の注意点まで徹底解説【設計・開発担当者向け】
ステンレス鋼(SUS系)との比較
SKD61とステンレス鋼(SUS420J2など)は、金型分野において腐食対策の選択肢として比較検討されます。主な違いは、耐食性と高温特性です。
ステンレス鋼は耐食性に優れる一方、高温での強度保持力は工具鋼ほど高くありません。SKD61は高温強度に優れますが耐食性では劣ります。加工性では、ステンレス鋼は加工硬化しやすい一方、SKD61は焼なましをすれば比較的加工しやすいです。コスト面では、一般的にステンレス鋼の方が高価です。
防錆が最優先であればステンレス鋼、そうでなければSKD61という判断が現場で行われます。
設計判断に役立つ特性比較表
以下に、SKD61と代表的な比較対象であるSKD11、および参考としてステンレス鋼(SUS420系)の主要特性の比較をまとめます。
| 特性項目 | SKD61(熱間工具鋼) | SKD11(冷間工具鋼) | ステンレス鋼(SUS420系) |
| 硬さ(HRC)※熱処理後 | 53〜56程度 | 58〜62程度 | 〜50程度(最大硬化時) |
| 常温での耐摩耗性 | 高い(汎用金型として十分) | 非常に高い(長寿命) | 中程度 |
| 高温環境での強度保持 | 優れる(300℃でも強度維持) | 劣る(200℃以上で低下) | やや劣る(400℃以上で低下) |
| 靱性(粘り強さ・衝撃耐性) | 高い(熱衝撃にも強い) | 中〜低(硬いがもろい) | 中程度(靱性はあるが硬度低め) |
| 耐食性(さびにくさ) | 低い(要防錆処理) | やや高い(Cr約12%) | 非常に高い(ステンレスの長所) |
| 被削性(加工のしやすさ) | 焼なまし状態では比較的良好 | やや難(加工硬化少ないが硬度高い) | 難しい(加工硬化・粘り有り) |
| 材料コスト・流通性 | 標準的(入手容易、改良鋼も多い) | 標準的(入手容易、代替鋼種多い) | 高め(特殊用途向けで価格高) |
| 主な用途例 | ダイカスト金型、熱間鍛造型、熱間工具類 | プレス金型、刃物、パンチ、樹脂金型 | 腐食性樹脂用金型、食品医療用部品 |
設計の注意点
ここでは、設計者・調達担当者が押さえておきたいSKD61選定時の注意点をまとめます。
熱処理を前提とした公差・形状設計
SKD61の性能を最大限に引き出すためには、熱処理が不可欠です。熱処理による寸法変化や変形を考慮し、研削仕上げ代を確保し、公差を設定しましょう。
熱処理時の割れやひずみを避けるため、鋭角なコーナーや急激な肉厚の変化を避け、コーナーにはRを設け、肉厚を均一にする設計が望ましいです。特に精密部品ではこれらの配慮が品質を左右します。
熱処理後に切削加工はほぼ不可能になるため、ネジ穴やキー溝などの加工は必ず熱処理前に完了させる必要があります。
コストと供給安定性の観点
SKD61の材料コストは性能に見合った範囲であるものの、調達ロットや市場状況で変動します。特殊鋼のため一般構造用鋼材より高価である一方、国内外のメーカーから供給されているため入手性は良好です。
コスト面で重要なのは加工後の費用です。大型金型では熱処理や研削仕上げに費用がかかりますが、これにより金型寿命の延長や製品品質の向上が期待できるため、長期的にはコストメリットが大きい傾向にあります。
加工時・使用時の注意点
SKD61素材の加工時および使用時には、いくつか注意点があります。
加工時は熱処理によるひずみを考慮した設計と、精密部品では熱処理後の研磨工程計画が必要です。使用時は錆びやすいため、長期保管や高湿度環境下では防錆処理が必須で、金型では防錆油の塗布や定期的な錆除去が重要です。
また、大きな治具や金型を常温から急激に高温環境へ投入すると割れの原因となるため、予熱にも注意が必要です。
代替材を検討すべきケース
SKD61は優れた材料であるものの、用途によっては他の材質の方が適している場合があります。具体例は以下のとおりです。
- 非常に高い耐摩耗性が必要な場合:SKD11や高速度鋼
- 腐食環境下:ステンレス系金型材料
- 加工性を優先する試作・少量生産:プリハードン鋼
- 600℃以上の高温で使用する場合:ニッケル基超合金やセラミックスなどの専用耐熱材料
SKD61加工の見積もり依頼は「meviyマーケットプレイス」へ
SKD61の部品製作には、ぜひメビーマーケットプレイスをご活用ください。
メビーマーケットプレイスは、製造パートナーからあらゆる機械加工部品を手配できる日本最大級の製造業マーケットプレイスです。ミスミのIDがあれば新規の口座開設なしで加工部品を手配できます。
3Dもしくは2Dの設計データをアップロードし、加工方法・材質・表面処理などの見積条件を設定すると、条件に合ったパートナーが提案されます。複数の加工会社に個別で問い合わせる手間を削減できるほか、見積もりや出荷日などの条件を比較・検討する時間も短縮できます。
まとめ
本記事では、熱間ダイス鋼SKD61について、基本的な特性から具体的な用途、加工上の注意点までを解説しました。
SKD61はJIS規格に定められた合金工具鋼で、特に高温環境下での強度と靱性に優れています。この特性は、クロム、モリブデン、バナジウムといった添加元素によってもたらされ、ダイカスト金型や熱間鍛造金型といった過酷な環境で真価を発揮します。
そのメリットは、優れた耐熱衝撃性や幅広い加工適性、性能とコストのバランスの良さです。一方で、熱処理後の加工難度の高さや、熱処理に伴う寸法変化のリスクといったデメリットも存在し、設計段階で考慮しなければなりません。
SKD61を最大限に活用するには、熱処理を前提とした公差設計や、割れを防ぐための形状の工夫が欠かせません。また、SKD11やステンレス鋼といった他の材料との特性を正しく比較し、用途に応じて最適な材料を選定する視点も必要です。
この記事で解説したSKD61の情報を、材料選定や金型設計、調達業務にぜひご活用ください。